 村田和人 ロングインタビュー (PART1)
村田和人 ロングインタビュー (PART1)
約13年ぶりのニューアルバム「NOW
RECORDING+」をリリースした、村田和人さんへのロングインタビュー。
そのPART1。
(2008年9月1日/都内某所にて/インタビュアー:TERA@moment)
大学2、3年の頃で、フリーのプロデューサーが「村田君いいよ〜!レコード作りましょう!」っていう話で来て。で、結構そういう風にディレクターが来るパターンが多かったので、もうすっかり自分の中では「自分たちの思い通りにならないディレクターは駄目」みたいな感じになっていて、そのプロデューサーと会った時も「あなたがプロデューサーじゃ駄目」みたいな。「え、どういうこと?じゃあ誰だったらいいわけ?」っていうことで、「山下達郎さんだなぁ、やっぱり!」って言ったらそのプロデューサーが達郎さんを知っている人で、親切に「じゃあ紹介してあげるよ」って言うんでRVCレコードで会うことになって。
TERA(以下:T):では。よろしくお願いします。
村田和人(以下:M):よろしくお願いします。
T:まずは生まれた場所を教えて下さい。
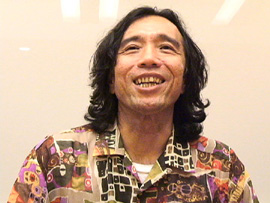
M:え〜、東京品川区の中延というところです。
T:なるほど。ご兄弟は?
M:兄弟は弟が1人。
T:そうですか。おいくつぐらいですか?
M:今三つ下なんで51歳ですかね、弟が。
T:小さい頃はわりと一緒に遊んだり?
M:一緒に遊ぶというよりは、村田が同じぐらいの年の子達と遊ぶのについて回る形ですね。だからあんまり一緒に遊んだ感じじゃないですけど。
T:幼稚園時の一番遠い記憶は何ですか?
M:幼稚園。幼稚園はね、嫌いだったんですよ、何故か。で、毎日泣いて戻るっていう感じ。幼稚園連れてくんだけど戻って来ちゃうっていう。自分では全然理由覚えてなかったんですけど後から親に聞いたら、その幼稚園の先生が嫌いだったみたいで。で、幼稚園の先生が代わったら毎日行くようになったっていってましたから。だからそれが幼稚園の時の記憶ですね。
T:お友達とかは、いっぱい居たんですか?
M:そうですね、誰とでも仲良く遊んだんで。その後幼稚園の友達が中学校とかで同級生になってたりとかして。小学校は違っていて、中学校でまた会って親交を深めてっていう形でしたね。
T:小学校はちゃんと行けた感じですか?
M:行きました!小学校はばっちり。(笑) でも大体学校自体が好きなんですよね。勉強はそんなに好きじゃないですけど、学校自体は友達関係が。誰とでも仲良くなっちゃう、クラス替えをしても。
T:なるほど。小学校低学年の時の遊びってどんな遊びでした?
M:ドッジボールですかねぇ。校庭でドッジボール。後は、古い時代ですから、馬跳びっていう遊びですね。ドッジボール、馬跳び、そのぐらいだったと思いますけど。小学校の間中そんな感じだったと思います。
T:そうですか。ラジオとかテレビの記憶は?
M:テレビがうちに来たのが小学校3年とか4年ぐらい。でも村田が住んでた東京の品川の中延という辺りでは一番早かったと思います。うちが電気工事のお店だったんで、電気関係の方から買ったんだと思うんですけど。で、家に帰って夜になりますよね。テレビを茶の間で見てると近所の方から電話がかかってきて「今お宅、何見てんの?」「今日はプロレス見てます」とかって。「今から行きます!」とか言ってその人が来て(笑)そうやってプロレスのときはその当時力道山という人がいて、とても人気のあるスポーツだったんで、自分の家の茶の間のテレビを5〜6人の人が一緒に見てるっていう感じだったですね。白黒ですけど。
T:なるほど。他に何か番組とかで覚えてるのはありますか?
M:やっぱり村田はプロレスよりも…ディズニーが。多分金曜日だったと思うんですよ、プロレスの日とディズニーの日とあったんですよ。それの入れ替わりだったんで、プロレス中止にならないかなっていつも思ってましたねぇ。
T:あの、「ディズニーランド」って番組ですね。
M:そうです。で、ディズニーでも冒険の国とかおとぎの国とか。中でもアニメが見たかったんですよね。だから冒険の国だとなんかすごくがっかりして“洞窟見たくない〜”とかって思ったんですけどね。(笑)
T:小学校上級生になって、部活動とかは?
M:部活はねぇ、村田が小学校の時は部活がなかったんですね。野球が好きだったんで、友達同士でよく野球に行って違う小学校の子供たちと土曜日の午後とか日曜日の朝とかそういうときに野球の試合をやって。音楽もよく聴いてましたね。まだ蓄音機、ステレオじゃないですね。ポータブル蓄音機の時代。
T:それは家に元々あったんですか?
M:家にはなかったんですよ。友達の家にあったんで、友達のお姉ちゃんのなんですけど、それが聴きたくて友達の家にもう毎日行ってましたねぇ。ちょうどビートルズの「ロック・アンド・ロール・ミュージック」とか、それからベンチャーズのものとか、そういうのを聴きたいが為に友達の家に集まって。
T:一番最初にビートルズとかベンチャーズとか聴いた記憶ってありますか?
M:ビートルズは、そのお姉ちゃんのところで「ロック・アンド・ロール・ミュージック」が一番最初に聴いた歌だったんですけど。それまではテレビで坂本九さんとかパラダイスキングとかその辺りの人が歌う、わりとまだソフトな歌い方しか知らなかったんで。ビートルズの歌を聴いた時は、特に「ロック・アンド・ロール・ミュージック」でジョンレノンが「ワー」ってシャウトしてるの聴いて“うわっ、全然違う!これすごい!”ってもう凄いカルチャー・ショックだったです。小学校5年だと思うんですけど、凄いカルチャー・ショックを受けたの覚えてますね。「こういう音楽あるの、これすごい」って。でも楽器をやろうとは思わなくて、とにかく凄い音楽があるんだって、それしか知らなかったんで、とにかくそれが聴きたいんで毎日その家に行っては「ロック・アンド・ロール・ミュージック」聴かせろって…。そればっかり聴いてましたね。
T:中学に入って何か新しく始めた事はありましたか?
M:中学入ってすぐ、6月にビートルズが来日して。それでラジオで毎日毎日ビートルズの特集番組が組まれていて、「ロック・アンド・ロール・ミュージック」聴いたのと同じように、ビートルズの曲1曲聴く毎に、新しく聴く曲聴く曲にみんなカルチャー・ショック受けてましたね。「うわすごいぞ!すごいぞ!」って。それまで聴いてた日本の音楽とか、まぁ日本の音楽でも60年代最初の頃のヒット・ポップス、アメリカン・ポップスだったりするんですけど、それとはもうまるで異質で、全然違う感覚で音楽を聴いたんですよね。それでビートルズの来日公演があってテレビで見て「わ、すごいわぁ!」って思って、それで楽器を始めようと思って。それで次の日に近所のディスカウント・ショップみたいな所に行って、三千円のエレキ・ギターを買って。それからですね、楽器を弾き始めたのは。
T:やっぱり、最初はビートルズの?

M:そう、ビートルズのコピー。それからすぐローリング・ストーンズを知って、ローリング・ストーンズとビートルズで。もう2年間くらいずっとそればっかりですね。
T:一緒に演奏する友達とかは?
M:一応バンドは作ってたんですよ。作ってたんですけど、誰も何も弾けない。(笑)
T:なるほど。(笑)
M:中学校一年生でましてや教則本もないし教えてくれる人間も回りにいなくて、一応「お前がベースな!お前がドラムな!」って言ってその友達の家に集まるんですけど、ベースな!って言ったやつはベース持ってないし、ドラムはドラム持ってない(笑)かろうじて村田のエレキ・ギター1本と、もう1人のアコースティック・ギターがあって、2本だけでみんなで歌っているっていうバンドでしたね。で、ドラムはダンボール。ダンボールを3つくらい組み合わせて“ド・ド・タ・ド・ド・ド・ド・タ”みたいな、そういうバンドです(笑)
T:(笑)。 何か発表の場とかあったんですか?
M:発表は中学校の時はないですね。中学校のときはエレキ・ギター持ってそういう音楽を聴いてる、楽器を持ってる、演奏してる、もうそれだけでいわゆる不良の扱いだったんですよ。だからしばらく担任の男の先生に居残りさせられて。で、毎日“音楽をやめろ”“楽器を売れ”そればっかりずーっと言われ続けました。
T:へぇ〜。家はどうだったんですか?
M:家は全然、放任で、「あ、そう、好きなの〜どうぞ〜」みたいな感じでやらせてもらってたんですけど、学校はうるさかったですね。
T:なるほど。バンド名とかは決めたりしてたんですか?
M:ゴブリンズだったような気がする。活動って言っても、当時はみんな集まってアレ歌おう、コレ歌おうっていう感じで。しかも急に言うからコードなんかろくに弾けないですからね、見よう見まねで弾いて。その当時「若者たち」って歌が流行ってて、もう1人のギターが「村田、若者たちはな、Cだけでいけるぜ!」って言って(笑)最初から最後までCだったんですよ、コードが。う〜ん、確かにって(笑)で、ずーっといけるんですけど、最後だけどうもなんか違うような気がするって感じたのは覚えてますけど。
T:なるほど。で、中学卒業する頃になると進路的に高校とかはどう考えてたんですか?

M:当時は進学っていうか、あんまり勉強に熱心な時代じゃないんで、何の気なしに都立高校に入って。で、音楽も引き続きやっていたんですけれども。都立がその当時70年安保闘争っていうか学生運動真っ最中の時代で。高校生は普通は関係ないんですけど、その当時大学で学生運動が凄く盛んで、その大学生が高校までやってきて、雷神部隊っていうのが。で、高校がロック・アウトしちゃったんですよ。1年生の夏休み明けだったと思うんですけど、さぁこれから2年3年と続いていくのにいきなり高校1年で学生紛争に巻き込まれて、毎日集会。体育館に集まって毎日学生集会みたいなのが。だから勉強もなんにも、1年の1学期しか学校で授業がなくて、2学期3学期はずーっと体育館だったんですけど。でも、まだ中学生みたいなものじゃないですか、高校生1年って。なので生徒集会でヒゲが濃いような3年生が出てきて「それは欺瞞だ!」っていう集会風景で、一年生の村田たちには欺瞞が分からないんで「おいおいおい、欺瞞ってどういうこと?どういうこと?誰か知ってる?誰か知ってる?」みたいな。言う言葉が、欺瞞ひとつとっても分からない。だからそのうち参加しなくなるんです、集会に。何をしていたかというと、学校に行かないで、毎日村田の家に高校の友達が集まってきては麻雀をやったりとか音楽をやったりとか。音楽はだからその時にわりと一緒に村田のうちで演奏して。高校ってわりと村田の実家に近かったんですよね。それで朝、出席を取ったら体育館に行かないで「村田のうちにくるやつー!」っていうのでみんな集まって来てたりしたんです。だからもう後半、夏休み明けてちょっと集会出て、自分たちの能力の範囲を超えてるんで村田の家で遊ぼうっていう風潮になって。それでたまに学校に行ってちょっと作業とかやって家に帰ってくると、村田がいなくてももう既に麻雀が始まってたりしてましたから(笑)勝手に友達が入ってっていうことが。で、麻雀をこっちでやってると、こっちでは音楽を好きな人は色んな音楽を聴いたりとか。だから楽器弾ける人は弾いて、その楽器弾ける人にコードを教わったりとか。そういうサークルになってましたね、村田家が。
T:それが高校一年生の時に?
M:高校一年。で、2年から授業形態が戻ったんですけど、もう一年の生活に馴染んだ連中は戻れないですよね。(笑)
T:(笑)
M:だから2年3年ってずっとそういう暮らしでした。学校に行く、出席を取る。大体高校の授業って2時間授業なんですよね、数学が2時間続いたり。で、一時間目に出席取ったら「もう今日はじゃあこれだけで」って友達と一緒に帰っちゃう。そういう暮らしだったんでもう学力は全然つかず。高校卒業して、2年浪人しちゃうんですけれど。
T:では、音楽的にはかなりその間上達してるんですよね?
M:そうですね。その当時がわりと、ハード・ロック、ブリティッシュ・ハード・ロックのブームっていうか、それが好きだったんで。レッド・ツェッペリンをやったりフリーって言うバンドのカヴァーをやったり。そこら辺のブリティッシュ・ハードが好きでやってて。で、ソロとかコードもちゃんと弾ける人がいて、そいつからいろいろ教わったりとかしたり。
T:中学とはまた違うバンドを組んでたんですか?
M:そうですね。もう中学のときのバンドは全然どっかに消えてましたから。3年生くらいのときからもう独学に、1人だけの音楽の世界になってたんで。
T:高校の時のバンドの名前は、なんて言うんですか?
M:いや、バンド名は特になくて、学園祭の度に作られるバンドでしたね。だから学園祭のときに自分の彼女を作るだとか、自分の彼女に見せるだとか、もうそのためだけに作られたバンドで(笑)去年はこういう音楽やったから、今年はこういうのでモテようぜ!っていう。最近出たこれがかっこいいんだよ!とか言いながらそういう感じで。だから掛け持ちも多くて、ビートルズのコピーをやってるバンドから、「村田、お前ベースが弾けるからベース弾いてコーラスやってくれ」とか、「一応アメリカン・ロックやってるバンドなんだけど、ステッペン・ウルフってかっこいいんだよ」とかって言いながら「じゃあ「Born
To Be Wild」だったら俺参加する〜」とかっいうことで参加したりとか。でも基本はブリティッシュ・ハードでした。
T:なるほど。まだオリジナルとかは作ってない?
M:作ってないですね。もう洋楽一本だったんで。中学最初の頃は色んなコード覚えるんで日本の曲もやったんですけど、もう途中からはビートルズ、ストーンズ、それからクリームとか洋楽ばっかりになって、とにかく日本の音楽は歌謡曲みたいっていう風に聴こえてたんですね、自分の耳には。で、日本語はかっこ悪いって思っていたんで、もうオリジナルなんか絶対駄目って、日本語のオリジナルなんか作れないって思っていたんです。で、2年か3年くらいのときに村田の家に集まる音楽仲間が、はっぴいえんどのアルバムを持ってきてそれを聴かせてもらったときに、またカルチャー・ショックを受けて。「凄いんじゃない?!彼らって!これ日本語だよね?」みたいな。難しい日本語いっぱい使っていたんで、ちょっと知らない日本語もいっぱいありましたけど。
T:(笑)
M:でもすごく、日本語に聴こえないくらいかっこいい。で、一緒に音楽やっていた仲間と、こういうのだったら俺たちもオリジナルで作って日本語で歌えるんじゃないの?っていうことになって。そこからオリジナルを作り始めたんですよ。高校2、3年だと思います。
T:なるほど。最初はどんな感じで作り始めたんですか?
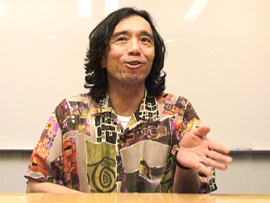
M:もう、とりあえずはっぴいえんどが好きだったんで、まずそのコードをコピーして好きな曲を歌って、今度はそのコードで違うメロディーを作るみたいなやり方ですね、最初は。で、そのうちコードをいっぱい覚えるようになって、このコードを使うとどういう曲が作れるとかっていうのをやってたんですけど、でも1人だとなかなか難しいんですよ。そこでギターを一緒に弾く仲間がいて、こんなコードを使ったらどういうメロディーが作れる?っていうのをお互いやり合ってるうちに、リズムだったりコード進行なんかの化学反応のさせ方みたいなものが分かってきて、どうすると曲がいっぱい出来るかっていうのをそのとき発見しましたね。
T:詞とかは?
M:詞はね、自分じゃなかなかむずかしくて、何か出来事があるまで曲だけがどんどん溜まっていって。で、そのとき付き合ってた人と何かがあると、それを最初は日記のように書いて、それをちょっと字数を合わせて、この詞は今までに作ったこの曲に合ってるかもしれないってそれで乗せていくっていう作業をしていて。だからオリジナルを早く完成させたいっていうのではなくて、何か詞が出来たときだけオリジナルが増えていくっていう。彼女とデートして待ちぼうけをくらいました、っていうのがあって、電話しても文句とか何も言えません!とか好きって言いたいですとか(笑)そういう思いがあって初めて詞が出来る。だからフィクションが書けないタイプですよね。
T:じゃあ、最初はラブ・ソングから入ったってことですか?
M:もうラブ・ソングしかないですね(笑)その時に好きだったか、その時々に付き合ってた女性との出来事ばっかりですね。
T:(笑)。その楽曲を人前で歌ったりすることも?
M:いや、その時はとても(できない)。例えば付き合ってた女の子が家に遊びに来たりするときもあるじゃないですか。
T:えぇ。
M:何か楽器を弾いてよ、とか言われると、学園祭ではあんな一生懸命うまく歌っていたのに、面と向かってマンツーマンだと歌えないんですよ。昔見た加山雄三さんの映画で唐突に加山雄三さんが歌い出して、すみちゃんが「あぁ〜!」みたいな感じになるのを描いているんですけど、自分じゃ出来ないんですよ。学園祭ではお客さんの中に混じって自分がいいなぁって思っている娘がいたりするのは逆にこれでもかっていけるんですけどね。マンツーマンは駄目だったですね。
T:で、卒業する頃は、もう次の進路は決めていたんですか?
M:絶対に大学に受からないって自信があったので、浪人だなって。だから高校卒業した1年目はどこも試験受けなかったです。もう浪人決定!みたいになってたんで。で、浪人して音楽がグッと深くなっちゃったんですよね。で、勉強しなきゃいけないんですけど、まず因数分解から始めるみたいな。理系だったんで、一応。一週間頑張って因数分解終わって、次は三角関数が出てきて。で、三角関数がまるで分からなかったんですよ。どういうこと?みたいな感じで全然わからない。それはやっぱり高校1年でロック・アウトした、そっから分かんらなくなってしまいましたね、対数とか。そこで勉強が止まるんですよいつも。で、また一ヶ月くらいして、「あ、やっぱり勉強やらなきゃ!」って思い直して、また因数分解から始めるんです(笑)
T:(笑)
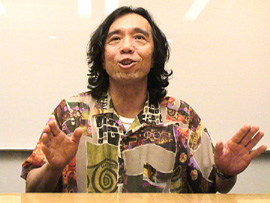
M:因数分解得意なんですよ、今でも、(笑)、「キング・オブ因数分解」って言われたことがあって。それで勉強やらない分、何してたかって言うと、もう1日ずーっと曲を作って。あとは新しく作ったオリジナルを多重録音するっていう作業が、それが楽しくて。で、カセットがまだあまり普及してなくてオープン・リールのデッキで。村田が持ってたオープン・リールのデッキには、レフト・チャンネルからライト・チャンネルにピンポンしながらミキシング出来るっていう機能があったんですね。(ダブル・カセットに置き換えれば)こっちのカセットからこっちのカセットに録音しながら、例えばギターをもう1本入れるっていう、そういう機能。だから当然モノラルだったんですけど。それで色んなコーラスを、例えばビートルズの自分の好きな曲のハーモニーをやってみようとか、それからインストゥルメンタルをちょっとやってみようとか。そのうち自分の作ったオリジナル曲にギターを入れてベースを入れて、そのときはベースを入れながらコーラスもやらなきゃいけないんですよね。あんまり音を重ねるとホワイト・ノイズが増えちゃって“シーーー”がすごくなっちゃうんで4本が限界。だからギター弾きながらコーラス入れて、ベース弾きながらコーラス入れて、最後にリード弾きながらリード・ヴォーカル入れて、みたいな感じで多重録音したんですけど。
T:それは、どこかに提出したりとかは?
M:いや全然、その当時はなんのコンテストも無かったはずですね。せいぜいヤマハ系の「コッキーポップ」みたいなものとかで、あまり一般から広くオーディションで曲を受け付けてそれからデビューさせるってシステムじゃなかったと思います。とにかく勉強は嫌だった半面、音楽はむちゃくちゃ楽しかったんで、その分全部音楽に注ぎ込んで。だから2年浪人しちゃったんですけど、結局。その間すごい沢山の曲を書きましたね。
T:プロになっても歌われている曲は、その中にあるんですか?
M:ありますよ。だから、デビュー曲の「電話しても」はその時に作った作品で。で、今回、『NOW RECORDING+』で取り上げているのはその頃の曲を10曲ピック・アップして。まだもうちょっと、15〜16曲あったんですけど、それは作品としてこの世に出すクオリティに達してないという(笑)ことで、永遠のお蔵入りになったんですけどね。だからそもそもその「電話しても」って曲をはじめとして、19〜20歳の浪人時代に作った曲がいっぱいありました。自分でも音楽が楽しくて、オリジナル曲もいっぱい出来て、でも別にデビューは考えてなくて。とにかくバンドでやりたいっていう。バンドがやりたくて大学に入ったんですよ、その時は。で、大学ならどこでもいいと。三角関数から先に進まないようになっていたんでもう諦めて、文系でいこうと。でも試験勉強とか何もやってないんで、どっかいいところない?って言ったら、その当時英語しか試験科目がない埼獨協大学があって。「俺、英語なら結構得意だから出来ちゃうかも」って獨協大学を受けたら合格して。
T:で、大学生活はまずどんな感じだったんですか?
M:2年浪人してたじゃないですか。だからもう授業が嬉しくて嬉しくて。毎日朝9時からの授業で、東京の城南地区から埼玉の草加まで一時間ちょっとくらいかかるんですけど、朝7時起きして大学の授業に最初の半年くらいは全て出たと思いますね。規制されない生活だったでしょ?浪人生活って。
T:はい。
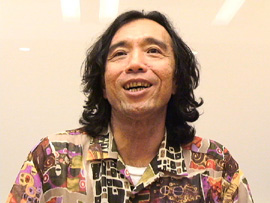
M:ほっとけば昼過ぎに起きてほっとけば朝の6時くらいに寝る生活だったんで。その学校の授業っていう規制された枠の中に逆に入るのが嬉しくて、最初の半年はもう本当に休まずに学校に通って。だから1年目とかほとんど全部優だったと思います。
T:サークルはすぐに音楽系のに入ったんですか?
M:サークルは軽音に入ったんですけど、最初に軽音のいわゆる新入生歓迎コンパに参加したときに、そのサークルの先輩と合わなくて。それで1日でやめちゃったんですよ、実は。それで、じゃあどうしようかなって思ったときに自分が浪人中に多重録音したテープ、これをカセットにして自分のクラスの音楽やりそうな、髪長くて「お前音楽やる?」って人に「ちょっと聞いて!これ、聞いて!」って配って。そうしたら「お前のオリジナル良いよ〜!」って人が現れて。
T:えぇ。
M:あっと言う間に。「バンドやろうぜ!このオリジナルならいけるよ!」とかって言われて、バンドが出来たんですけど、それがALMOND ROCCAっていうバンドなんですけど。その「いいよ!」って言われた曲は、後に村田のデビュー曲になる「電話しても」だったんですよ。「電話しても」って曲をすごく気に入って、これをメインでいこうって。で、その「電話しても」を評価してくれた人の家でミーティングしてる時に「そういえばさぁ、お前にそっくりな声と歌い方の人いるよ」って山下達郎さんがいたシュガー・ベイブのアルバムをそこで初めて聴かせてもらったんです。で、「Down
Town」を聴いて「えー!本当だ!」みたいな。声の質感とか歌い回しのちょっとした転がし方とか「うわーっ、似てる!本当だ!」って思って。でも悔しいから、そいつには「でもこの人ってさぁ、大瀧詠一さんのマネしてない?」とかって言いながら(笑)
T:(笑)
M:で、その後達郎さんにその話をしたときに「それはそうかもしれないけど、僕の後ろには大瀧詠一がいる。あなたの後ろにはこれから山下達郎が10年ついて回るから」と言われたんですけど、10年どころではなかったですねぇ。まだやっぱり村田の後ろには山下達郎の名前が見え隠れ(笑)
T:(笑)で、そのバンドの活動はまずどういう風に始まったんですか?

M:最初は渋谷にあったヤマハのエピキュラスっていうところでリハを始めて。バンドも高校の時の学園祭バンドぐらいしかやってないですから。そこから音をちゃんとまとめていくうちに、エピキュラスが主催のコンサートがあったんですよ。「エピキュラスを借りて練習してくれているアマチュア・バンドのみんな、月に一度フレンズコンサートっていうのをやってますよ!」っていう催しがあって「俺たちも2〜3ヶ月練習した後、一回参加してみようか?」「じゃあデモ・テープ録って出してくれるかどうか聞いてみよう」っていうことになって、それでそのデモを聴いてくれたヤマハの人がまたすごく「電話しても」を気に入ってくれて。「いい曲じゃないこれ!ポプコンにも出しなよ!」って言ってくれて。ポプコンがあったですね、その当時。それからその系列のイーストウエストに薦めてくれて。で、エピキュラスはプロ仕様の録音スタジオも備えていて、そこのエンジニアの人が「俺が口きいてあげるから、タダでデモ・テープ録ってあげるよ!」って言われて。多分高田馬場のBIG
BOXの中にあったスタジオで2曲、「電話しても」ともう一曲「涙枯れるまで」っていう曲。もう歌謡チックな歌詞なんですけど、その2曲を録ったんですよね。
T:で、それを何かに?
M:えぇ。それをポプコンとかイーストウエストに出したりとか。イーストウエストではその曲でエピキュラスの大会でグランプリを獲ったんですけど、でもその上の中野サンプラザでの大会には出られなかったんですよ、選考で落ちて。で、その後ライヴハウスに出ようって話になって、大学2年生くらいからはライヴハウス中心に渋谷の屋根裏、吉祥寺のシルバーエレファント、新宿ロフト、あと横浜の関内にあった放送局っていうライヴハウス、それから湘南にあったリトルジョージとか。いろんなライヴハウスで、デモを持っていくととりあえずどこでも出してくれるようになって。「俺たち、もうちょっと頑張ろうね、って言われなくなったよ!出してくれるようになった!」ってすごく喜んで。大体週に一本ぐらいずつのライヴやってましたね。
T:さらに何か音源を作るっていうのは?
M:そうですね、そのイーストウエストとか大会に出る為にスタジオを借りてちゃんとしたエンジニアの人に録ってもらうっていうお金が無かったんで、マルチ録音みたいな形でベーシストの家でドラムの音も録って、ベースもラインで録って一つずつ音を被せていって、オリジナルのデモとか作ったりしてたんですけど。その後あまり大会とかグランプリとかとは無縁だったですね。大学2年のときに確かグランプリを獲ったんですけど、その後はちょっとパッとしないで。でもライヴはまめに一杯やってました。
T:なるほど。大学生活は大丈夫だったんですか?
M:その後、一年の時の貯金が効いたんだと思うんですけど、嬉しくて通って全優だったじゃないですか。で、2年の時もある程度ちゃんと単位を全部取って。その時に余分に取れるとこは全部単位を取ったんですよ。で、単位が全部取れてたんで、3年4年はせいぜい週5時間とかぐらいの授業数でもう卒業の単位に足りちゃってたんですよね。
T:へぇ〜!じゃあもうバンド生活を?
M:そうですね、もうずーっとバンド。だから実家で起きるとレコーダーのあるベーシストの家にみんな集まって、その家が歯医者さんだったんですけど子供たちがバンドやってるんで「お前たち、部屋を防音にしてやろう」って1部屋防音にしてくれて。だから本当にお金をかけないでもう毎日リハーサルやっては、次のライヴのネタを作って、ライヴに出ては次の週のネタや新しいオリジナルを作ったり、それからカヴァーを増やしたりとかそういうのを2年間やって、それでかなり自力がついたって言うんですかねぇ。その当時は今のライヴ・ハウスの形態とは違って昼間1バンドだったんですよ。アマチュアは昼間の部で出るっていう。で、しかも1バンドで2時間はまかなうっていう。だからフル・ライヴをまかされるんで。お客も前の月と同じ曲をやると次の月はもう来てくれないんですよ。「またどうせ…。もう聞き飽きたよ、あの曲は」とかって言われちゃうんで。だから毎月毎月話のネタからカヴァーする曲のネタも変えてやっているうちに、新しい曲を聴いたらどう吸収して、どこがこの曲のリズムのポイント、アレンジのポイントだっていうのがすぐに感じられるようになってきましたね。
T:はい。
M:で、大事なのは、例えばこのベースのラインとベースのあそこのノリなんだよ!とか、そのドラムの噛み合わせがあるからこの曲は成立してるとかっていう“感覚”なんですけど、もうすっかりその当時に出来るようになっていましたね。
T:ライヴの時のカヴァー曲はどんなものだったんですか?
M:カヴァー曲は、イーグルスとかドゥービー・ブラザーズとか、ウエストコースト系が多かったですね。とか、あと自分の知ってる友達のバンドのオリジナル曲とか演奏したりしてましたね。だから昔だと、達郎さんが(伊藤)銀次さんの曲をやったりとか、鈴木茂さんの曲をやる感覚で、自分の好きな友達のバンドの曲を「この曲使わせて!」とかって使ったりとかしてました。
T:その後プロになるバンドとかアーティストとか、その頃から絡んだりしてました?
M:その後プロになって、例えば早見優ちゃんのバックでずっとギターやっていた人とか、ブレッド&バターと一緒にギターをやってるとかそういう人はいましたけど。1人、ずっと村田のバンドでもギターを弾いてくれてたりとか、今回のアルバムでもエレキ・ギターを全部弾いている山本圭右君なんかは、パイパーっていうバンドで村田よりも先にデビューしていた人なんですけど、好きなギタリストだったんで村田がデビューした時に「是非村田のバックもやって!」って頼んで、もうそれから30年近く付き合ってますね。
T:その後のバンドの流れっていうのは?
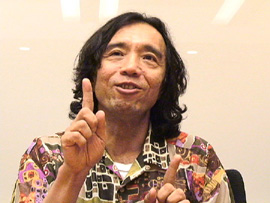
M:卒業と同時にみんな就職が決まってたんで、「あら?就職って、するもの?」みたいな。全然就職活動のやり方も知らなくて、卒業間際の1月とかにメンバーに聞いて「学校の就職部に行くんだよ」って言われて行って「就職ってどうやってするんです?」って聞いたら「あんた一月に来て何言ってんの!」って言われて、結局何にも就職しないで。バンドからも2人就職することになっていて「じゃあ解散」って言って解散して。で、4年間もうずーっとバンドをやってきたんでとりあえず、就職もせず、バンドもなく…フリーターでもやろうかな!って、大学卒業して24歳でフリーター(笑)でもその当時2つ仕事をやっていて、大卒の給料で16〜17万だったときに22〜23万になってたんで安心してやってたんですけど。そのうちの1つが、エレクトロ・
ハーモニックスっていうニューヨークの楽器の会社なんですけど。そこの会社が日本代理店を作りたいっていうのを知り合いから聞かされて「村田君、ちょっと社長の下でやってくれない?」って頼まれて、でも午前中は他のバイトがあるんで「午後からならいいよ」って言ったら「午後から出勤でいいみたいよ」っていう話で、それで午後からはその楽器屋さんで働いてましたね。で、それをやりながら半年ぐらいした時ですかね、元のバンドのベースの人が現れて「もう一回やろうぜ俺たち」っていうノリで(笑)「これからはもっとロックにいこうぜ!アメリカン・ロックだ、これからは!」って「そうか、今まではちょっとポップ・ポップだったもんね」って。曲調的にはシュガー・ベイブ的なものだったんで、「もうちょっとロックな曲を作ろう、ロックなバンドを作ろう!」って。「じゃあドラムはダブルだ!」ってダブル・ドラムで、ギター3人!!のトリプル・リード!みたいな(笑)
T:(笑)
M:打って変わっていきなりやってましたね、そういう感じの。
T:それが80年代入って?
M:そうですね、79年から81年くらいまで続いたんですけど。
T:その頃は日本のロック・シーンにわりといろいろ動きのあった頃ですよね。
M:多分、関西系の例えば上田正樹さんのサウス・トゥ・サウスとか、シュガー・ベイブが東京だとすると大阪の方の音楽がわりとバタくさくてロックくさくて、そういう音楽が当時のアマチュア・バンドにもすごく刺激を与えていた頃で、そういうものもあってうちもバタくさい、ウエストコーストやサザン・ロック的な音楽をやろう!っていうんでそういう形態でやり始めたんですけど。でもやっていくうちに、村田の感性の中にはポップなメロディーがあって、ガツガツとロックで押しまくる音楽に自分では違和感を感じ始めていて…。やっぱりポップが、コーラスが熱く出ちゃうような音楽がいいなって思ってたんですよね。で、その時に現れたのがRVCっていうレコード会社で達郎さんのレーベルのディレクターだった人だったんですよ。そのレーベルに遊びに行って、最初はデビューしようって話になるんですけど、その前に既に22歳ぐらいの時に、一番最初のエピキュラスで録ってもらった2曲のデモテープ「電話しても」と「涙枯れるまで」を村田は山下達郎さんに渡してるんですよね、1回。
T:え〜、それはどのタイミングで?
M:それは22歳ぐらいですから、大学2、3年の頃で、フリーのプロデューサーが「村田君いいよ〜!レコード作りましょう!」っていう話で来て。で、結構そういう風にディレクターが来るパターンが多かったので、もうすっかり自分の中では「自分たちの思い通りにならないディレクターは駄目」みたいな感じになっていて、そのフリーのプロデューサーと会った時も「あなたがプロデューサーじゃ駄目」みたいな。「え、どういうこと?じゃあ誰だったらいいわけ?」っていうことで、「山下達郎さんだなぁ、やっぱり!」って言ったらそのプロデューサーが達郎さんを知っている人で、親切に「じゃあ紹介してあげるよ」って言うんでRVCレコードで会うことになって。そういうことになると思わないでそういう機会をもらっちゃって「ひぇ〜!これ有り〜?!」みたいなもうバクバクな感じで達郎さんと会って。
T:はい。
M:で、その時にエピキュラスで録った「電話しても」と「涙枯れるまで」の2曲のデモテープを達郎さんに渡したんです。
T:なるほど。
M:そのフリーのプロデューサーとはしばらく、大学にいる間は連絡取ってたんですけど、別に達郎さんとは直接の連絡先を交換していなくて、気に入ってくれたかもわからないままフリーのプロデューサーともいつの間にか疎遠になって。達郎さんは「電話しても」をものすごく気に入ってくれていたらしくて、「この人、どうしちゃったんだろう」ってよく話してくれていたらしいんですけど。で、大学卒業後にそのRVCのディレクターとAIRレーベルに行った時に、まず最初に達郎さんのディレクターの小杉(理宇造)さんと再会して、その小杉さんも村田のことを覚えていてくれて「よく山下君と君の事を話してるんだよ!」っていうことで、それで達郎さんと会って「君が出てこなかったらこの歌は自分がカヴァーしようと思ってたんだよ」っていう話で。「出てきたんだったら、自分でやりなさい」ってデビューさせてもらったんです。
T:そこからアルバムを制作する過程っていうのは?
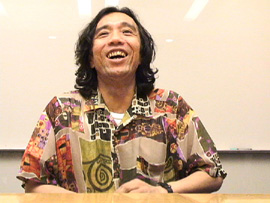
M:これがね、今言ってたAIRレーベルから最初はデビューする予定で作り始めて、その当時のRVCレコードでレコーディングが始まったんですよね。それが81年のことで、作り始めてとりあえず3ヶ月くらいゆるゆると作っていて、とりあえず全部アレンジも終わってRVCレコードの来年デビュー予定の新人ということで、全国的にRVCレコードの地方の営業所にも村田のカセット・テープが配られて。でも結局ここで止まっちゃって。ちょうどAIRレーベルがRVCから抜けてムーンレコードを作るっていう時期だったんですよね。で、元々AIRレーベルからデビューするはずだったんだから、村田はムーンレコードでデビューしなさいって言われて「いや、別に自分はどこからデビューしてもいいですけど」みたいな感じで。結局RVCの話はそこまででなくなって、村田のそれは全部ムーンレコードに引き継がれて、それでムーンレコードでデビューしたんです。82年に。
T:なるほど。
M:最初は達郎さんじゃなくて鈴木茂さんアレンジでデビュー・アルバムを作っていて。途中からディレクターが「やっぱり声質とか曲調とかメロディーのラインとか山下達郎と共通するところがある。でも山下達郎はもう売れてるから、そのまま出すと二番煎じになってしまう。そうすると君はとても損をするから、達郎さんにプロデュースしてもらいたいけど、デビュー・アルバムは違う人でいこう!」っていう話で。それで鈴木茂さんのや達郎さんのアレンジで、セルフ・プロデュースでアルバムは作られましたね。
T:では、この辺りで、PART2へ続きます。引き続き、宜しくお願いします!
M:宜しくお願いします!
PART1 END>>>
■村田和人オフィシャル・ブログ
ツアーの様子やメディアへの出演情報など、最新情報をいち早くゲットできます。
http://d.hatena.ne.jp/KAZ_MURATA/☆
|
New
!
デビュー前の1970年代〜80年代初頭に書き溜められた未発表曲たちに、新たな息吹を!約30年の時を経て完成した珠玉の1枚。まさに村田和人の音楽的ルーツがここにある。
ニュー・アルバム『NOW RECORDING+』
NAYUTAWAVE RECORDS / UPCH-20108 / 定価¥3,000(税込)
24bit デジタル・リマスター / ボーナス・トラック5曲追加 / 村田和人コメント掲載 / 監修:村田和人/土橋一夫
村田和人、13年ぶりのニュー・アルバムとなる本作は、プロとしてデビューする1982年より前のアマチュア時代に書き溜められていた未発表曲を新たにレコーディングし、甦らせたものです。若き日の村田和人の感性や当時のテイストが詰まった楽曲の中には、デビュー前に既にライヴで披露されていたナンバーも含まれており、その後の活躍を予感させる興味深い楽曲が満載です!
本作は2008年4月に自主制作盤『NOW RECORDING』として発表されましたが、今回新たに貴重なボーナス・トラック5曲(全て未発表音源)を加え、24bitでデジタル・リマスタリングし、ジャケットも一新してタイトルも『NOW
RECORDING+』となって登場。若き日の村田和人のテイストをお楽しみ下さい。
村田和人さんの詳しいインフォメーションは、オフィシャルブログまで。
|

 |

 momentのオリジナルグッズを販売しています。
momentのオリジナルグッズを販売しています。
 #69
Talk&Interview
#69
Talk&Interview #69
#69 momentのオリジナルブログです。
momentのオリジナルブログです。 #69
music
#69
music
![]() 村田和人 ロングインタビュー (PART1)
村田和人 ロングインタビュー (PART1)![]()
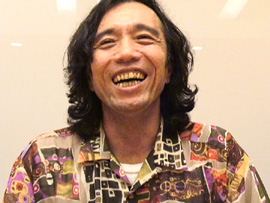
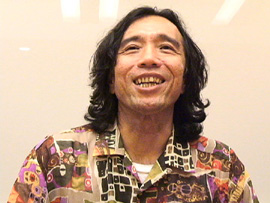 M:え〜、東京品川区の中延というところです。
M:え〜、東京品川区の中延というところです。 M:そう、ビートルズのコピー。それからすぐローリング・ストーンズを知って、ローリング・ストーンズとビートルズで。もう2年間くらいずっとそればっかりですね。
M:そう、ビートルズのコピー。それからすぐローリング・ストーンズを知って、ローリング・ストーンズとビートルズで。もう2年間くらいずっとそればっかりですね。 M:当時は進学っていうか、あんまり勉強に熱心な時代じゃないんで、何の気なしに都立高校に入って。で、音楽も引き続きやっていたんですけれども。都立がその当時70年安保闘争っていうか学生運動真っ最中の時代で。高校生は普通は関係ないんですけど、その当時大学で学生運動が凄く盛んで、その大学生が高校までやってきて、雷神部隊っていうのが。で、高校がロック・アウトしちゃったんですよ。1年生の夏休み明けだったと思うんですけど、さぁこれから2年3年と続いていくのにいきなり高校1年で学生紛争に巻き込まれて、毎日集会。体育館に集まって毎日学生集会みたいなのが。だから勉強もなんにも、1年の1学期しか学校で授業がなくて、2学期3学期はずーっと体育館だったんですけど。でも、まだ中学生みたいなものじゃないですか、高校生1年って。なので生徒集会でヒゲが濃いような3年生が出てきて「それは欺瞞だ!」っていう集会風景で、一年生の村田たちには欺瞞が分からないんで「おいおいおい、欺瞞ってどういうこと?どういうこと?誰か知ってる?誰か知ってる?」みたいな。言う言葉が、欺瞞ひとつとっても分からない。だからそのうち参加しなくなるんです、集会に。何をしていたかというと、学校に行かないで、毎日村田の家に高校の友達が集まってきては麻雀をやったりとか音楽をやったりとか。音楽はだからその時にわりと一緒に村田のうちで演奏して。高校ってわりと村田の実家に近かったんですよね。それで朝、出席を取ったら体育館に行かないで「村田のうちにくるやつー!」っていうのでみんな集まって来てたりしたんです。だからもう後半、夏休み明けてちょっと集会出て、自分たちの能力の範囲を超えてるんで村田の家で遊ぼうっていう風潮になって。それでたまに学校に行ってちょっと作業とかやって家に帰ってくると、村田がいなくてももう既に麻雀が始まってたりしてましたから(笑)勝手に友達が入ってっていうことが。で、麻雀をこっちでやってると、こっちでは音楽を好きな人は色んな音楽を聴いたりとか。だから楽器弾ける人は弾いて、その楽器弾ける人にコードを教わったりとか。そういうサークルになってましたね、村田家が。
M:当時は進学っていうか、あんまり勉強に熱心な時代じゃないんで、何の気なしに都立高校に入って。で、音楽も引き続きやっていたんですけれども。都立がその当時70年安保闘争っていうか学生運動真っ最中の時代で。高校生は普通は関係ないんですけど、その当時大学で学生運動が凄く盛んで、その大学生が高校までやってきて、雷神部隊っていうのが。で、高校がロック・アウトしちゃったんですよ。1年生の夏休み明けだったと思うんですけど、さぁこれから2年3年と続いていくのにいきなり高校1年で学生紛争に巻き込まれて、毎日集会。体育館に集まって毎日学生集会みたいなのが。だから勉強もなんにも、1年の1学期しか学校で授業がなくて、2学期3学期はずーっと体育館だったんですけど。でも、まだ中学生みたいなものじゃないですか、高校生1年って。なので生徒集会でヒゲが濃いような3年生が出てきて「それは欺瞞だ!」っていう集会風景で、一年生の村田たちには欺瞞が分からないんで「おいおいおい、欺瞞ってどういうこと?どういうこと?誰か知ってる?誰か知ってる?」みたいな。言う言葉が、欺瞞ひとつとっても分からない。だからそのうち参加しなくなるんです、集会に。何をしていたかというと、学校に行かないで、毎日村田の家に高校の友達が集まってきては麻雀をやったりとか音楽をやったりとか。音楽はだからその時にわりと一緒に村田のうちで演奏して。高校ってわりと村田の実家に近かったんですよね。それで朝、出席を取ったら体育館に行かないで「村田のうちにくるやつー!」っていうのでみんな集まって来てたりしたんです。だからもう後半、夏休み明けてちょっと集会出て、自分たちの能力の範囲を超えてるんで村田の家で遊ぼうっていう風潮になって。それでたまに学校に行ってちょっと作業とかやって家に帰ってくると、村田がいなくてももう既に麻雀が始まってたりしてましたから(笑)勝手に友達が入ってっていうことが。で、麻雀をこっちでやってると、こっちでは音楽を好きな人は色んな音楽を聴いたりとか。だから楽器弾ける人は弾いて、その楽器弾ける人にコードを教わったりとか。そういうサークルになってましたね、村田家が。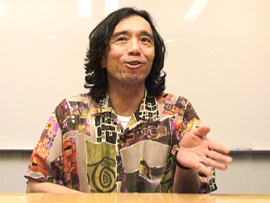 M:もう、とりあえずはっぴいえんどが好きだったんで、まずそのコードをコピーして好きな曲を歌って、今度はそのコードで違うメロディーを作るみたいなやり方ですね、最初は。で、そのうちコードをいっぱい覚えるようになって、このコードを使うとどういう曲が作れるとかっていうのをやってたんですけど、でも1人だとなかなか難しいんですよ。そこでギターを一緒に弾く仲間がいて、こんなコードを使ったらどういうメロディーが作れる?っていうのをお互いやり合ってるうちに、リズムだったりコード進行なんかの化学反応のさせ方みたいなものが分かってきて、どうすると曲がいっぱい出来るかっていうのをそのとき発見しましたね。
M:もう、とりあえずはっぴいえんどが好きだったんで、まずそのコードをコピーして好きな曲を歌って、今度はそのコードで違うメロディーを作るみたいなやり方ですね、最初は。で、そのうちコードをいっぱい覚えるようになって、このコードを使うとどういう曲が作れるとかっていうのをやってたんですけど、でも1人だとなかなか難しいんですよ。そこでギターを一緒に弾く仲間がいて、こんなコードを使ったらどういうメロディーが作れる?っていうのをお互いやり合ってるうちに、リズムだったりコード進行なんかの化学反応のさせ方みたいなものが分かってきて、どうすると曲がいっぱい出来るかっていうのをそのとき発見しましたね。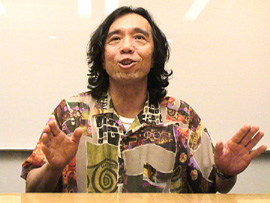 M:因数分解得意なんですよ、今でも、(笑)、「キング・オブ因数分解」って言われたことがあって。それで勉強やらない分、何してたかって言うと、もう1日ずーっと曲を作って。あとは新しく作ったオリジナルを多重録音するっていう作業が、それが楽しくて。で、カセットがまだあまり普及してなくてオープン・リールのデッキで。村田が持ってたオープン・リールのデッキには、レフト・チャンネルからライト・チャンネルにピンポンしながらミキシング出来るっていう機能があったんですね。(ダブル・カセットに置き換えれば)こっちのカセットからこっちのカセットに録音しながら、例えばギターをもう1本入れるっていう、そういう機能。だから当然モノラルだったんですけど。それで色んなコーラスを、例えばビートルズの自分の好きな曲のハーモニーをやってみようとか、それからインストゥルメンタルをちょっとやってみようとか。そのうち自分の作ったオリジナル曲にギターを入れてベースを入れて、そのときはベースを入れながらコーラスもやらなきゃいけないんですよね。あんまり音を重ねるとホワイト・ノイズが増えちゃって“シーーー”がすごくなっちゃうんで4本が限界。だからギター弾きながらコーラス入れて、ベース弾きながらコーラス入れて、最後にリード弾きながらリード・ヴォーカル入れて、みたいな感じで多重録音したんですけど。
M:因数分解得意なんですよ、今でも、(笑)、「キング・オブ因数分解」って言われたことがあって。それで勉強やらない分、何してたかって言うと、もう1日ずーっと曲を作って。あとは新しく作ったオリジナルを多重録音するっていう作業が、それが楽しくて。で、カセットがまだあまり普及してなくてオープン・リールのデッキで。村田が持ってたオープン・リールのデッキには、レフト・チャンネルからライト・チャンネルにピンポンしながらミキシング出来るっていう機能があったんですね。(ダブル・カセットに置き換えれば)こっちのカセットからこっちのカセットに録音しながら、例えばギターをもう1本入れるっていう、そういう機能。だから当然モノラルだったんですけど。それで色んなコーラスを、例えばビートルズの自分の好きな曲のハーモニーをやってみようとか、それからインストゥルメンタルをちょっとやってみようとか。そのうち自分の作ったオリジナル曲にギターを入れてベースを入れて、そのときはベースを入れながらコーラスもやらなきゃいけないんですよね。あんまり音を重ねるとホワイト・ノイズが増えちゃって“シーーー”がすごくなっちゃうんで4本が限界。だからギター弾きながらコーラス入れて、ベース弾きながらコーラス入れて、最後にリード弾きながらリード・ヴォーカル入れて、みたいな感じで多重録音したんですけど。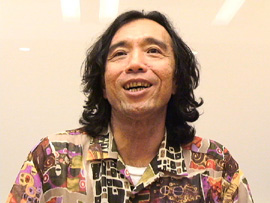 M:ほっとけば昼過ぎに起きてほっとけば朝の6時くらいに寝る生活だったんで。その学校の授業っていう規制された枠の中に逆に入るのが嬉しくて、最初の半年はもう本当に休まずに学校に通って。だから1年目とかほとんど全部優だったと思います。
M:ほっとけば昼過ぎに起きてほっとけば朝の6時くらいに寝る生活だったんで。その学校の授業っていう規制された枠の中に逆に入るのが嬉しくて、最初の半年はもう本当に休まずに学校に通って。だから1年目とかほとんど全部優だったと思います。 M:最初は渋谷にあったヤマハのエピキュラスっていうところでリハを始めて。バンドも高校の時の学園祭バンドぐらいしかやってないですから。そこから音をちゃんとまとめていくうちに、エピキュラスが主催のコンサートがあったんですよ。「エピキュラスを借りて練習してくれているアマチュア・バンドのみんな、月に一度フレンズコンサートっていうのをやってますよ!」っていう催しがあって「俺たちも2〜3ヶ月練習した後、一回参加してみようか?」「じゃあデモ・テープ録って出してくれるかどうか聞いてみよう」っていうことになって、それでそのデモを聴いてくれたヤマハの人がまたすごく「電話しても」を気に入ってくれて。「いい曲じゃないこれ!ポプコンにも出しなよ!」って言ってくれて。ポプコンがあったですね、その当時。それからその系列のイーストウエストに薦めてくれて。で、エピキュラスはプロ仕様の録音スタジオも備えていて、そこのエンジニアの人が「俺が口きいてあげるから、タダでデモ・テープ録ってあげるよ!」って言われて。多分高田馬場のBIG
BOXの中にあったスタジオで2曲、「電話しても」ともう一曲「涙枯れるまで」っていう曲。もう歌謡チックな歌詞なんですけど、その2曲を録ったんですよね。
M:最初は渋谷にあったヤマハのエピキュラスっていうところでリハを始めて。バンドも高校の時の学園祭バンドぐらいしかやってないですから。そこから音をちゃんとまとめていくうちに、エピキュラスが主催のコンサートがあったんですよ。「エピキュラスを借りて練習してくれているアマチュア・バンドのみんな、月に一度フレンズコンサートっていうのをやってますよ!」っていう催しがあって「俺たちも2〜3ヶ月練習した後、一回参加してみようか?」「じゃあデモ・テープ録って出してくれるかどうか聞いてみよう」っていうことになって、それでそのデモを聴いてくれたヤマハの人がまたすごく「電話しても」を気に入ってくれて。「いい曲じゃないこれ!ポプコンにも出しなよ!」って言ってくれて。ポプコンがあったですね、その当時。それからその系列のイーストウエストに薦めてくれて。で、エピキュラスはプロ仕様の録音スタジオも備えていて、そこのエンジニアの人が「俺が口きいてあげるから、タダでデモ・テープ録ってあげるよ!」って言われて。多分高田馬場のBIG
BOXの中にあったスタジオで2曲、「電話しても」ともう一曲「涙枯れるまで」っていう曲。もう歌謡チックな歌詞なんですけど、その2曲を録ったんですよね。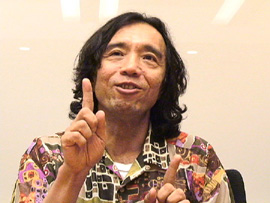 M:卒業と同時にみんな就職が決まってたんで、「あら?就職って、するもの?」みたいな。全然就職活動のやり方も知らなくて、卒業間際の1月とかにメンバーに聞いて「学校の就職部に行くんだよ」って言われて行って「就職ってどうやってするんです?」って聞いたら「あんた一月に来て何言ってんの!」って言われて、結局何にも就職しないで。バンドからも2人就職することになっていて「じゃあ解散」って言って解散して。で、4年間もうずーっとバンドをやってきたんでとりあえず、就職もせず、バンドもなく…フリーターでもやろうかな!って、大学卒業して24歳でフリーター(笑)でもその当時2つ仕事をやっていて、大卒の給料で16〜17万だったときに22〜23万になってたんで安心してやってたんですけど。そのうちの1つが、エレクトロ・
ハーモニックスっていうニューヨークの楽器の会社なんですけど。そこの会社が日本代理店を作りたいっていうのを知り合いから聞かされて「村田君、ちょっと社長の下でやってくれない?」って頼まれて、でも午前中は他のバイトがあるんで「午後からならいいよ」って言ったら「午後から出勤でいいみたいよ」っていう話で、それで午後からはその楽器屋さんで働いてましたね。で、それをやりながら半年ぐらいした時ですかね、元のバンドのベースの人が現れて「もう一回やろうぜ俺たち」っていうノリで(笑)「これからはもっとロックにいこうぜ!アメリカン・ロックだ、これからは!」って「そうか、今まではちょっとポップ・ポップだったもんね」って。曲調的にはシュガー・ベイブ的なものだったんで、「もうちょっとロックな曲を作ろう、ロックなバンドを作ろう!」って。「じゃあドラムはダブルだ!」ってダブル・ドラムで、ギター3人!!のトリプル・リード!みたいな(笑)
M:卒業と同時にみんな就職が決まってたんで、「あら?就職って、するもの?」みたいな。全然就職活動のやり方も知らなくて、卒業間際の1月とかにメンバーに聞いて「学校の就職部に行くんだよ」って言われて行って「就職ってどうやってするんです?」って聞いたら「あんた一月に来て何言ってんの!」って言われて、結局何にも就職しないで。バンドからも2人就職することになっていて「じゃあ解散」って言って解散して。で、4年間もうずーっとバンドをやってきたんでとりあえず、就職もせず、バンドもなく…フリーターでもやろうかな!って、大学卒業して24歳でフリーター(笑)でもその当時2つ仕事をやっていて、大卒の給料で16〜17万だったときに22〜23万になってたんで安心してやってたんですけど。そのうちの1つが、エレクトロ・
ハーモニックスっていうニューヨークの楽器の会社なんですけど。そこの会社が日本代理店を作りたいっていうのを知り合いから聞かされて「村田君、ちょっと社長の下でやってくれない?」って頼まれて、でも午前中は他のバイトがあるんで「午後からならいいよ」って言ったら「午後から出勤でいいみたいよ」っていう話で、それで午後からはその楽器屋さんで働いてましたね。で、それをやりながら半年ぐらいした時ですかね、元のバンドのベースの人が現れて「もう一回やろうぜ俺たち」っていうノリで(笑)「これからはもっとロックにいこうぜ!アメリカン・ロックだ、これからは!」って「そうか、今まではちょっとポップ・ポップだったもんね」って。曲調的にはシュガー・ベイブ的なものだったんで、「もうちょっとロックな曲を作ろう、ロックなバンドを作ろう!」って。「じゃあドラムはダブルだ!」ってダブル・ドラムで、ギター3人!!のトリプル・リード!みたいな(笑)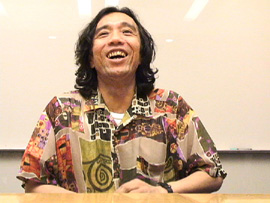 M:これがね、今言ってたAIRレーベルから最初はデビューする予定で作り始めて、その当時のRVCレコードでレコーディングが始まったんですよね。それが81年のことで、作り始めてとりあえず3ヶ月くらいゆるゆると作っていて、とりあえず全部アレンジも終わってRVCレコードの来年デビュー予定の新人ということで、全国的にRVCレコードの地方の営業所にも村田のカセット・テープが配られて。でも結局ここで止まっちゃって。ちょうどAIRレーベルがRVCから抜けてムーンレコードを作るっていう時期だったんですよね。で、元々AIRレーベルからデビューするはずだったんだから、村田はムーンレコードでデビューしなさいって言われて「いや、別に自分はどこからデビューしてもいいですけど」みたいな感じで。結局RVCの話はそこまででなくなって、村田のそれは全部ムーンレコードに引き継がれて、それでムーンレコードでデビューしたんです。82年に。
M:これがね、今言ってたAIRレーベルから最初はデビューする予定で作り始めて、その当時のRVCレコードでレコーディングが始まったんですよね。それが81年のことで、作り始めてとりあえず3ヶ月くらいゆるゆると作っていて、とりあえず全部アレンジも終わってRVCレコードの来年デビュー予定の新人ということで、全国的にRVCレコードの地方の営業所にも村田のカセット・テープが配られて。でも結局ここで止まっちゃって。ちょうどAIRレーベルがRVCから抜けてムーンレコードを作るっていう時期だったんですよね。で、元々AIRレーベルからデビューするはずだったんだから、村田はムーンレコードでデビューしなさいって言われて「いや、別に自分はどこからデビューしてもいいですけど」みたいな感じで。結局RVCの話はそこまででなくなって、村田のそれは全部ムーンレコードに引き継がれて、それでムーンレコードでデビューしたんです。82年に。
