| blog | talk & interview | short films | music | magazine | special issue | shop | about "moment" | contact us |
|
bbs
 |
about moment moment 概要 (DVD/イベント/『moment strings quartet」etc.) |
shop
 momentのオリジナルグッズを販売しています。
momentのオリジナルグッズを販売しています。
talk & interview
momentと交流のある方々へのインタビュー
 #70
Talk&Interview
#70
Talk&Interview
村田和人(PART2)
約13年ぶりのニューアルバム、「NOW RECORDING+」
をリリースした、村田和人さんのロングインタビュー。
そのPART2。
contact us
 #70
#70blog
 momentのオリジナルブログです。
momentのオリジナルブログです。music
momentに関連したミュージシャン、バンド等を紹介します。
 #70
music
#70
music
高橋結子 (PART1)
様々なバンド活動やアーティストサポートを続けている、
ドラム&パーカッション高橋結子さん。
ロングインタビュー。PART1。
 |
magazine |
| #70 CLIP:「月刊:種ともこ」第九号 LIVE:「瞬間的 弦楽四重奏団 -2008年秋公演-」 CD:「YANCY:New Album 『TASOGARE-JOHN』」 連載コラム:TERA'S SOUNDTRACK REVIEW #70/ 「遠すぎた橋」 連載:「DOGMA #4」 by ミヤサキワタル |
|
| short films |
||||||
|
||||||
![]() 村田和人 ロングインタビュー (PART2)
村田和人 ロングインタビュー (PART2)![]()
約13年ぶりのニューアルバム「NOW
RECORDING+」をリリースした、村田和人さんへのロングインタビュー。
そのPART2。
(2008年9月1日/都内某所にて/インタビュアー:TERA@moment)
|
|
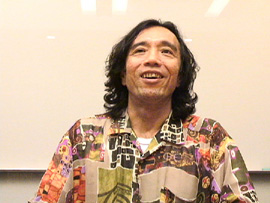 |
村田和人(KAZUHITO
MURATA) ロングインタビュー(PART2) Talk&Interview
#70 |
|
|
| 村田和人 ロングインタビュー (PART2) |
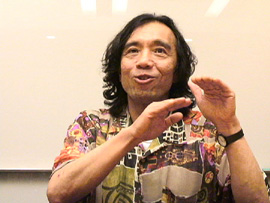 M:はい。ファースト・アルバムのプロデュースを達郎さんにやってもらいたいのはやまやまだったんですけど、でも初めから達郎さんの色で全てを作ってしまうと、絶対にこれから長い間、村田のサウンドは達郎さんと比較され続けられるだろうから、ということで敢えて鈴木茂さんとか井上鑑さんに参加してもらいました。だからファースト・アルバムは、鈴木茂アレンジがあって井上鑑アレンジがあって、という構成になったんです。最初はRVCから発売するはずだったんですけど、そのうちにムーンレコードで発売するっていうことになって、次の年の4月までデビューを待つことになったんで、いっぱい作りかえる時間があって。で、その辺りから達郎さんもまた加わって、アレンジを変える曲あり、達郎さんのギター・ソロに差し替える作業あり、コーラスを山下達郎アレンジに差し替えるものあり、といった感じで、そこかしこに達郎さんがアレンジを加えてくれたものも、ファースト・アルバムにいっぱい詰まっているんです。
M:はい。ファースト・アルバムのプロデュースを達郎さんにやってもらいたいのはやまやまだったんですけど、でも初めから達郎さんの色で全てを作ってしまうと、絶対にこれから長い間、村田のサウンドは達郎さんと比較され続けられるだろうから、ということで敢えて鈴木茂さんとか井上鑑さんに参加してもらいました。だからファースト・アルバムは、鈴木茂アレンジがあって井上鑑アレンジがあって、という構成になったんです。最初はRVCから発売するはずだったんですけど、そのうちにムーンレコードで発売するっていうことになって、次の年の4月までデビューを待つことになったんで、いっぱい作りかえる時間があって。で、その辺りから達郎さんもまた加わって、アレンジを変える曲あり、達郎さんのギター・ソロに差し替える作業あり、コーラスを山下達郎アレンジに差し替えるものあり、といった感じで、そこかしこに達郎さんがアレンジを加えてくれたものも、ファースト・アルバムにいっぱい詰まっているんです。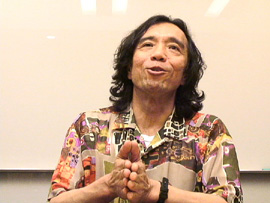 M:そうですね。最初のちゃんとしたツアーはその年にやったと思うんですけど。東・名・阪、北海道も行ったのかな。覚えてないですけど、福岡・北海道辺りも2年目、3年目に行ったような気がするんですけれど、5大都市ですね。バンドもギタリストはアマチュア時代から知っていた人で、パーカッションはその作品から移って、里村(美和)から代わって、固定メンバーになりました。最初はやっぱりアマチュア時代の勢いのまんまプロのライヴをやっていた感じがあって。アマチュア時代には、2日続けてライヴなんてあまりないじゃないですか。
M:そうですね。最初のちゃんとしたツアーはその年にやったと思うんですけど。東・名・阪、北海道も行ったのかな。覚えてないですけど、福岡・北海道辺りも2年目、3年目に行ったような気がするんですけれど、5大都市ですね。バンドもギタリストはアマチュア時代から知っていた人で、パーカッションはその作品から移って、里村(美和)から代わって、固定メンバーになりました。最初はやっぱりアマチュア時代の勢いのまんまプロのライヴをやっていた感じがあって。アマチュア時代には、2日続けてライヴなんてあまりないじゃないですか。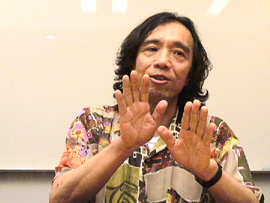 M:本当は85年に発表するアルバムがあったんですけど、達郎さんが「そういう風にやるんだったら、僕にもアイディアがあるから、また山下達郎プロデュースでやらせなさい」って。やってくれるんだったらもう1回一緒にやりたいですね〜って待っていたらスケジュールが合わなくて、そうしたら今度はディレクターが「このままいくと夏には難しいよね」って話になって。「夏に難しいって言われても…じゃあ今年はなしで?」っていう風になって。そのアルバムに用意してた曲はほとんど香坂みゆきちゃんに提供して。香坂みゆきちゃんがアルバム『FAIRWAY』の半分に村田の曲を使ってくれたんですよ。で、村田のアルバムが出ないまま2年経っちゃって、その間ムーンレコードの中でディレクターが代わったんです。前のディレクターは音楽的だったんですけど、今回のディレクターが割とコマーシャルとかビジネス的なディレクターで、視点がまた違ったりするんですよ。「村田はもう2年出してないんだから、半端なことやっても受け入れてもらえないよ」って。じゃあ、どうするの?達郎さんプロデュース?っていうと「もう駄目!達郎プロデュースでも!」なんていうディレクターで(笑)、だったら「アメリカでやるんだな」とかって言いながら、別に何か勝算とか目算があって言ってるわけじゃないんです。ただアメリカでやるっていうその響きに惹かれて(笑)、アメリカ録音になりました。
M:本当は85年に発表するアルバムがあったんですけど、達郎さんが「そういう風にやるんだったら、僕にもアイディアがあるから、また山下達郎プロデュースでやらせなさい」って。やってくれるんだったらもう1回一緒にやりたいですね〜って待っていたらスケジュールが合わなくて、そうしたら今度はディレクターが「このままいくと夏には難しいよね」って話になって。「夏に難しいって言われても…じゃあ今年はなしで?」っていう風になって。そのアルバムに用意してた曲はほとんど香坂みゆきちゃんに提供して。香坂みゆきちゃんがアルバム『FAIRWAY』の半分に村田の曲を使ってくれたんですよ。で、村田のアルバムが出ないまま2年経っちゃって、その間ムーンレコードの中でディレクターが代わったんです。前のディレクターは音楽的だったんですけど、今回のディレクターが割とコマーシャルとかビジネス的なディレクターで、視点がまた違ったりするんですよ。「村田はもう2年出してないんだから、半端なことやっても受け入れてもらえないよ」って。じゃあ、どうするの?達郎さんプロデュース?っていうと「もう駄目!達郎プロデュースでも!」なんていうディレクターで(笑)、だったら「アメリカでやるんだな」とかって言いながら、別に何か勝算とか目算があって言ってるわけじゃないんです。ただアメリカでやるっていうその響きに惹かれて(笑)、アメリカ録音になりました。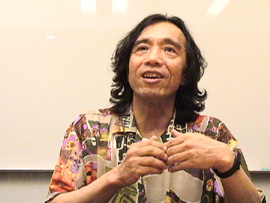 M:前回の初めてのロサンゼルス・レコーディングが自分で納得のいくものになって、じゃあこれは同じやり方でいこう、っていうことになって、ディレクターと話をして。で、もう最初から向こうでオケだけを作って日本に持ち帰ろう、っていうことになって(笑)。その方が歌もゆっくり歌えていいので。で、プロデュースしてくれたのがロニー・フォスターっていうスティーヴィー・ワンダーなんかのツアーのキーボードをやっている人で。そのロニー・フォスターが前のアルバムの『Showdown』の時は、村田がデモ・テープをヘッド・アレンジした状態で持っていったから「お前のアレンジがちゃんとしてたから、俺はやることがなくてつまらなかった、今度はお前がギター一本で歌っている歌を俺に送れ。俺がナイスなアレンジをしてやる!」って言うんで、今回は送ったんですけど。で、ロサンゼルスに着いて明日からレコーディングで、ロニー・フォスターの家に行って「はぁ〜い!アレンジ進んでるかな〜?」なんて言ったら「ごめんね〜、まだ出来てないんだ〜!」って。「うっそぉぉ!!!」みたいな(笑)。「明日からレコーディングだよ?!」「そうそうそうそう!だからこれから2人でやろうよ!」「えぇ!俺も?!」みたいな。
M:前回の初めてのロサンゼルス・レコーディングが自分で納得のいくものになって、じゃあこれは同じやり方でいこう、っていうことになって、ディレクターと話をして。で、もう最初から向こうでオケだけを作って日本に持ち帰ろう、っていうことになって(笑)。その方が歌もゆっくり歌えていいので。で、プロデュースしてくれたのがロニー・フォスターっていうスティーヴィー・ワンダーなんかのツアーのキーボードをやっている人で。そのロニー・フォスターが前のアルバムの『Showdown』の時は、村田がデモ・テープをヘッド・アレンジした状態で持っていったから「お前のアレンジがちゃんとしてたから、俺はやることがなくてつまらなかった、今度はお前がギター一本で歌っている歌を俺に送れ。俺がナイスなアレンジをしてやる!」って言うんで、今回は送ったんですけど。で、ロサンゼルスに着いて明日からレコーディングで、ロニー・フォスターの家に行って「はぁ〜い!アレンジ進んでるかな〜?」なんて言ったら「ごめんね〜、まだ出来てないんだ〜!」って。「うっそぉぉ!!!」みたいな(笑)。「明日からレコーディングだよ?!」「そうそうそうそう!だからこれから2人でやろうよ!」「えぇ!俺も?!」みたいな。 M:ムーンレコードは先ほど言ったようにRVCから独立する形で出来たんですけど、当初のムーンレコードには、独自のパワーとか考え方があったんですが、5枚目の頃には少しずつ普通のレコード会社と同じようなやり方になってきていて。レコード会社と村田とが刺激的じゃない関係になってきていて、季節がきたら音源作って“はい、プロモーション終わり、じゃあライヴ、よろしくー”みたいなそういう感じで、うーん…いまいち自分でどうなんだろう?って感じて。で、村田も含めて最初からムーンレコードを作ってきた人たちが、徐々に抜けていった時代だったので、村田も抜けようかなって。で、いろいろ話をもらって東芝EMIに移籍という形になったんですよね。
M:ムーンレコードは先ほど言ったようにRVCから独立する形で出来たんですけど、当初のムーンレコードには、独自のパワーとか考え方があったんですが、5枚目の頃には少しずつ普通のレコード会社と同じようなやり方になってきていて。レコード会社と村田とが刺激的じゃない関係になってきていて、季節がきたら音源作って“はい、プロモーション終わり、じゃあライヴ、よろしくー”みたいなそういう感じで、うーん…いまいち自分でどうなんだろう?って感じて。で、村田も含めて最初からムーンレコードを作ってきた人たちが、徐々に抜けていった時代だったので、村田も抜けようかなって。で、いろいろ話をもらって東芝EMIに移籍という形になったんですよね。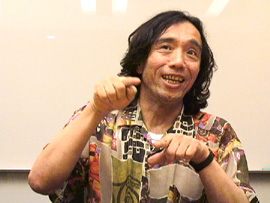 M:そうですね。基本はもう常に夏を意識して、っていうか夏の音楽を作ろう!じゃなくて自分の好きな世界が夏なんですよね、音楽的にも。だから湿ってたりとか重かったりとか、それ自体が自分の好みじゃないんですよ、きっと。あと、マイナーだったりとか。自分が夏っていう季節がすごく好きなのもあるし、それと自分の音楽が=(イコール)だったんですよね、思考と夏。だから必然的に出来てくるものが夏に聴き易いものになったんだと思うんですが。
M:そうですね。基本はもう常に夏を意識して、っていうか夏の音楽を作ろう!じゃなくて自分の好きな世界が夏なんですよね、音楽的にも。だから湿ってたりとか重かったりとか、それ自体が自分の好みじゃないんですよ、きっと。あと、マイナーだったりとか。自分が夏っていう季節がすごく好きなのもあるし、それと自分の音楽が=(イコール)だったんですよね、思考と夏。だから必然的に出来てくるものが夏に聴き易いものになったんだと思うんですが。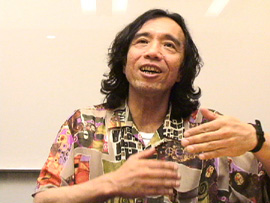 M:結果的にはやっぱり、すごいなって思うアレンジが半分、自分でもう一回やり直したいって思うアレンジが半分。だから、いいところだけ取りたい感じですよね。そのアレンジの根本のアイディアからして「あの曲がこういう風になるの?!すごい!」って思うのと「あの曲がこういう風になって、あ…こっちの方が良かった」って思うのと。だから、難しいです。人のアレンジでやるのは。
M:結果的にはやっぱり、すごいなって思うアレンジが半分、自分でもう一回やり直したいって思うアレンジが半分。だから、いいところだけ取りたい感じですよね。そのアレンジの根本のアイディアからして「あの曲がこういう風になるの?!すごい!」って思うのと「あの曲がこういう風になって、あ…こっちの方が良かった」って思うのと。だから、難しいです。人のアレンジでやるのは。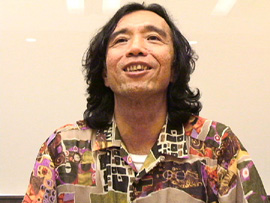 M:ええ。毎月1回で6曲、アロハ・ブラザースで作ったんですけど。だから毎月杉君と会ってはそんな感じで曲を作って「これはなんかさ、おシャンソンにして!」とか「アコーディオン、バラバラバラ〜!おフランスに行きませんか〜」みたいな感じで杉君が言って、「あ、じゃあだったらさぁ、宝塚チックにして、ここはみんなでユニゾンで歌っちゃうとか!」っていうアイディアを出しながらアレンジしてレコーディングして。
M:ええ。毎月1回で6曲、アロハ・ブラザースで作ったんですけど。だから毎月杉君と会ってはそんな感じで曲を作って「これはなんかさ、おシャンソンにして!」とか「アコーディオン、バラバラバラ〜!おフランスに行きませんか〜」みたいな感じで杉君が言って、「あ、じゃあだったらさぁ、宝塚チックにして、ここはみんなでユニゾンで歌っちゃうとか!」っていうアイディアを出しながらアレンジしてレコーディングして。| New
! デビュー前の1970年代〜80年代初頭に書き溜められた未発表曲たちに、新たな息吹を!約30年の時を経て完成した珠玉の1枚。まさに村田和人の音楽的ルーツがここにある。 ニュー・アルバム『NOW RECORDING+』 NAYUTAWAVE RECORDS / UPCH-20108 / 定価¥3,000(税込) 24bit デジタル・リマスター / ボーナス・トラック5曲追加 / 村田和人コメント掲載 / 監修:村田和人/土橋一夫 村田和人、13年ぶりのニュー・アルバムとなる本作は、プロとしてデビューする1982年より前のアマチュア時代に書き溜められていた未発表曲を新たにレコーディングし、甦らせたものです。若き日の村田和人の感性や当時のテイストが詰まった楽曲の中には、デビュー前に既にライヴで披露されていたナンバーも含まれており、その後の活躍を予感させる興味深い楽曲が満載です! 本作は2008年4月に自主制作盤『NOW RECORDING』として発表されましたが、今回新たに貴重なボーナス・トラック5曲(全て未発表音源)を加え、24bitでデジタル・リマスタリングし、ジャケットも一新してタイトルも『NOW RECORDING+』となって登場。若き日の村田和人のテイストをお楽しみ下さい。 村田和人さんの詳しいインフォメーションは、オフィシャルブログまで。 |
  |
|