| blog | talk & interview | short films | music | magazine | special issue | shop | about "moment" | contact us |
|
bbs
 |
about moment moment紹介 |
shop
talk & interview
momentと交流のある方々へのインタビュー
 #45
#45
リクオ (PART2)
1990年代からライブ活動やCDリリース等の音楽活動を展開、
幅広く色々なアーティスト、ミュージシャンと交流を持ち、
多岐に渡る音楽活動を続けている。ピアノマンで、
シンガーソングライター、リクオさんのロングインタビュー。PART2です!
contact us
 #45
#45blog
music
momentに関連したミュージシャン、バンド等を紹介します。
 #45
#45
YANCY (PART1)
KOTEZ&YANCYでは数多くの感動的なライブパフォーマンスを
展開。ソロとして「SONGS FROM SUNNY SKY」を、
クレイジーフィンガーズとしても、CD&DVDをリリースした
ばかりのピアノマンでシンガーソングライターYANCYさんのロングインタビュー。そのPART1。
 |
magazine |
| #45 CLIP:「06.08.30/SUMMER SESSION 2006 緊急レポート」 CLIP:「06.10.07+08/スギのカルパッチョを召し上がれ!!! 2-due-」 CLIP:「月刊ピカソvol.14/Official Bootleg Live PART3」 連載コラム:TERA'S SOUNDTRACK REVIEW #45/サボテンブラザース 散文詩:「#15/青い鳥」 KanaT |
|
| short films |
||||||
|
||||||
![]() リクオ(PART2)
リクオ(PART2)![]()
1990年代からライブ活動やCDリリース等の音楽活動を展開、幅広く色々なアーティスト、ミュージシャンと交流を持ち、
多岐に渡る音楽活動を続けているピアノマンでシンガーソングライター、リクオさんのロングインタビュー、そのPART2です!
(2006年7月26日/momentにて/インタビュアー:TERA@moment)
 |
リクオ
(Rikuo) 京都出身。 |
|
|
|
| リクオ・ロングインタビュー(PART2) |
 TERA(以下:T):では、PART2をよろしくお願いします。
TERA(以下:T):では、PART2をよろしくお願いします。
リクオ:はい。
T:デビュー後のソロのツアーについては?
リクオ:普通に東京、名古屋、京都、大阪あたりをレコ発ツアーで回るという感じでしたね。オレの場合そういうソロ活動と平行して、人のサポートも当時からやっていて、例えば友部正人さんのレコーディングとライヴに参加さしてもらったり。同世代の真心ブラザーズのレコーディングとツアーにも参加さしてもらう機会もあって、すごい楽しかったですね。遊びに行くような感覚で、ツアーにも参加さしてもらってましたね。
T:CDは、6年間で4枚に?
リクオ:いや、そのあとメーカーがポリドール移籍して5枚目を出してます。
T:コンスタントに1年に1枚くらい?
リクオ:そうですね、最初はコンスタントに1年に1〜2枚くらい出していって、移籍してからは、ちょっと間が空きましたね。2年ぐらいあったのかな。もっと空いたのかな。2年以上空いた。
T:そのメーカーが変わるあたりっていうのは何か?
リクオ:その頃から業界に対する不信感みたいなのが。自分が思ってたほどうまくいかない、好きな活動ができないみたいな、ストレスがだんだんたまってた中での移籍だったんです。で、移籍したのはいいんたけど、移籍してみたら、その新しいレコード会社内の体制が急に変わったりなんかして、それで自分を移籍させた担当の方の立場が悪くなって、そのうちに連絡取れなくなるとかね。まあ、ありがちなことですけど。それでレコーディングが全然進められない、レコーディングが始まってもまた中断したり、レコーディングが終わっても発売のめどが立たないとかね。その間はあまり活動ができなくて、仕事もなく、大阪で時間を持て余しているような感じでしたね。
T:上京ってその後ですよね。
リクオ:そうですね、その後ですね。
T:移籍して1枚出したあとぐらいですか。
リクオ:95年にポリドールからアルバムを出して、その翌年の96年に大阪のアパートを引き払って。
 T:それは何かきっかけがあったんですか?
T:それは何かきっかけがあったんですか?
リクオ:まず、大阪にいてては仕事が成り立たないということですね。人のサポートもやらないと食っていけないし、そのためには大阪にいると難しかったんですよね。あと、とにかく状況を変えたかったっていう気持ちもあったし。
T:ポリドールで2枚目は?
リクオ:1枚だけでしたね、結局。契約期間が残ってるんだけど、リリースのめどが全然立たないっていう状態だったので、多分当時自分が所属してた事務所側が、「それじゃ契約切ってくれ」という話をメーカー側にしたのかな。
T:ソロ活動より、そのサポート活動みたいなものの動きが活発になった?
リクオ:まあ、そっちの方がだんだん収入源になってたので。
T:リクオさんご自身としては、やっぱりアルバムをコンスタントに出したいという。
リクオ:そうですね。
T:そういう時期には曲作りは続いてるのですか?
リクオ:そうですね。でも、当時は曲作りも試行錯誤してましたね。ホリドールからアルバムを出す時は、プロデューサーの方がついて、いろんな注文があったので、まあそのアドバイスにそって曲作りにもにトライしてましたね。今のままではダメなんだなっていう気持ちが自分にもあったし。で、当時は仕事がなくて、けっこう時間もあったんで、曲作り以外にCD聴いてたり本読んだり、考え事する時間がたくさんあったんですよ。毎日昼過ぎに起きて、夕方に部屋を出て、鞄に本とかノートとか詰め込んで、喫茶店に行って、そこで時間を過ごして、夜にスーパーで買い物して帰るみたいな(笑)、そういう暮らしを続けてて。そういう貯めの時間を過ごせたのは、今となってはよかったかなという気はしますけどね。
T:べつに東京が住みにくいとかはありませんでしたか?
リクオ: 刺激がある街なんで、やっぱり仕事をするにはいいですね。いろんな人に会えるしね。好きですよ。ただずっと東京にばかりいると閉塞してきてしんどいですね。今みたいにしょっちゅうツアーに出て、東京と地方を行ったり来たりする暮らしが合ってるみたいですね。
 T:90年代後半に向かっての活動の流れは?
T:90年代後半に向かっての活動の流れは?
リクオ:それまでとは、ずいぶん変わりましたね。95年にポリドールから、メジャー・レーベルとしては最後のアルバムを出した年に、阪神淡路大震災と、オウムのサリン事件があったんですね。自分が悶々としてる時期と重なったこともあって、そのふたつの出来事がかなりショックで、いろいろ自分を見つめ直す機会になりましたね。わりとこう、オレは当時すごいまっすぐなとこがあったんで、思ったらそこをぐーっと突き進むみたいな、自分が思ってる正しいことをやろうという気持ちが強かったんですよ。でも、それによって見えてない景色というのが、ずいぶんあったんだなと思うようになって。「正しいこと」っていう部分で、自分の気持ちをしばっていて、楽しいこととか気持ちいいこととか、そういう基本的なところに自分でフタをしているような気がしてきたんですよね。そういう切り替えの時期が95〜96年ぐらいに、自分の中であって。まあ、やっぱり煮詰まってたんですね。もっといろんな世界を見て吸収した方がいいな、その為にはあんまりこだわりがあると視野が狭くなってしまうんで、一回それを捨てたところから、もう一回音楽を楽しむとこから始めようと。ハタチくらいの時に音楽に救われたという気持ちがすごく強かったんで、ある種の音楽にこだわり過ぎてしまうようなところがあって、他のものが見えなくなっていたところがあったんですよね。
T:ん〜なるほど。
リクオ:たとえばもっとティーン・エイジャー以前、幼稚園児とか小学生の頃になんの偏見もこだわりもなく歌謡曲とか聴いて楽しんでた時のああいう感覚だとか、最初にロック・ミュージックを聴いた時の、理屈じゃなくて五感を刺激されたり、すごく肉体に訴えかけられたりしてた、それを受け入れた感覚っていうのをどっかに忘れて、頭でっかちになってるようなところがあったので、そこを一回なんか、リセットというと都合が良すぎるんだけど、元のフラットな感覚に戻すとこから始めたいなと思ったんですよね。だからまず「楽しもう」っていう、そういうとこから音に接するように、心掛けたというか。オウムの一連の事件とか、震災っていうのがそういう気持ちになるきっかけにはなってましたね。それでまたバンドがやりたくなったんですよね。それも今までのソロ活動でやってた音楽とは違うことがやりたくて、ピアノとドラムとベースのシンプルなトリオ編成のバンドをソロ活動と平行してやってみたいなと思うようになって。
T:なるほど。
リクオ:96年から2年間、オリジナル・ラブのサポートをやったりして、クラブ・ミュージックって呼ばれるような、新しいダンス・ミュージックに触れる機会が増えたんです。オリジナル.ラブの田島クンは、当時の先端のダンス・ミュージックにリンクしている人間だったし、とにかく色んな音楽を吸収することにどん欲で、学ぶところがあったし、刺激をもらいましたね。当時のオリジナル・ラブは大体初秋から初冬にかけて年40本近いツアーを行ってたんですが、ツアー中は、ステージでも、オフ・ステージでも遊ぼうと決めたんです。ステージ上では、プレイだけじゃなくて、いかにライヴ・バフォーマンスで自分を魅せるかっていうことを考えるようになって、ステージ.アクションも楽しみながら考えてましたね。その頃からグラサンをし出したんです。それまでずっと帽子だったんですけどね。ライヴが終わった後は他のサポート.メンバーと夜の街にくり出して、地元のクラブを探して、そこでガンガン音楽を浴びながら、思いっきり飲んで、踊って、騒いでっていう日々を繰り返してたんです。そういう環境に身を置いてみて、自分は元々ロックンロールというダンス・ミュージックが好きだったんだなっていうことを思い出したんですよ。それで、「フィジカルに訴える、理屈を越えたダンス・ミュージックをもう一度やりたい」と思うようになったんです。
T:変わってきた事、新たな展開は?
リクオ:その頃から肉体に訴えかけるダンス・ミュージックと、ある種の洗練された音楽、バート・バカラックであるとかブラジル音楽、ボサノバであるとか、そういう音楽も好んで聴くようになって、打ち込みから生音まで、なんでもいいやみたいな状態で、音楽を聴く幅がすごい広がってたんですよ。で、そういう吸収したものを出せる場というか、実験できる場としてもバンドをやろうと。最初は「リクオ&ヘルツ」っていう、ソロ活動の一環みたいな感じでやってたんですよ。ベースの寺岡信芳は、元々アナーキーっていうパンクバンドでベース弾いてた人ですけど、ファンクとか、ソウルにも造詣が深くて、とても柔軟な志向を持ってる人なんです。「リクオ&ヘルツ」を始めて1年後くらいに、ドラマーが代わって、当時20代前半の坂田学という非常に才能豊かなドラマーが参加してくれたんです。この3人だったら面白い化学反応が起こるなと思って、それやったらもうソロとは全然別物の、本格的なバンドとして、活動して行こうということで、バンド名も「The
Herz」と改名して、で活動し出したんですよね。
で、どんどんソロとは音楽性も離れていって。でも、そのヘルツでの活動が自分のソロ活動にも随分とフィード・バックされていましたね。
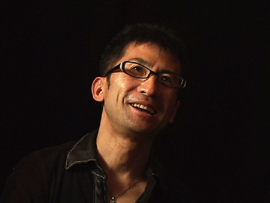 T:CDの形には。
T:CDの形には。
リクオ:うん、アルバムを2枚、4曲入CDを1枚。他にクラブユースのアナログ盤を2枚、数枚のコンピアルバムにも参加してます。須永辰夫さんによるリミックスが収録されたアナログ盤は、クラブでDJがかなり回してくれていましたね。
T:制作はどういう感じで行なわれたんですか?
リクオ:最初は作った時は、ライヴハウスにハードディスク・レコーダーを持ち込んで、2枚目のアルバムはエンジニアの自宅スタジオでプロトゥールスを使って録りました。
T:楽曲的にはリクオさんが作った楽曲?
リクオ:他のメンバーが作った曲もありましたけど、ほとんどの楽曲は、ベーシックをオレが作っていって、みんなでアレンジ考えてというやり方でしたね。
T:90年代後半は「The Herz」でずっと活動を?
リクオ:ヘルツを結成して98年に事務所を離れるんですね。まあメーカーの契約が96年には切れて、当時の音楽事務所ていうのは、メジャー・レーベルからの援助金、契約金で、成り立っている部分が強かったので、メジャーとの契約が切れて、援助金が出ないとなると、苦しいんですよね。メーカーとの契約が切れてもしばらくは、事務所に所属してたんですけど、とうとう「もう給料出せないけど、歩合制でならできるけど、どうする?」っていう話になりまして。当時自分の担当だったスタッフも事務所をやめるって言うんで、オレもいる意味がないな思って、8年間お世話になった事務所を離れて、フリーになったんです。
それで、どうやって食っていこうかなと考えて。人のサポート、セッション・マンをメインにしてやっていくというのは自分には向いてないし、一番やりたいことではないなと。やはり自分がフロントマンとして活動したかったんで、CDデビューする前のやり方に戻って、まず、自分でライブをブッキングして、ツアーを回ればいいんじゃないかと思ったんですね。
T:なるほど。
リクオ:オレがラッキーだったのは、デビュー前に、地元大阪で活動していた有山じゅんじさんであるとか憂歌団のみなさん、石田長生さん、友部正人さんであるとか高田渡さんといった1回り上の世代のミュージシャンのインディヘンドな活動、草の根のネットワークを生かした、メジャーに頼らない活動の仕方っていうのを見ていたし、体験してたんです。オレが初めての体験したツアーが、有山じゅんじさんと2人車一台で、100席に満たないライヴスポットを回るツアーだったんです。そういう活動の仕方を体験して、ある程度のやり方っていうのもわかっていたので、「また基本に戻ってやってみようかな」と。それでまあいろんなつてでお店に連絡して、音源を送って、それでブッキングしてもらってというところから始めて。もうひとつラッキーだったのは、'98年に事務所を辞める前に、自分の最後のマネージャーだった人が、「リクオはもうライヴをやらなきゃ食って行く方法がなくなるから、なるべくちっちゃい店でもライヴした方がいいよ」っアドヴァイスしてくれて、地方の店もブッキングしてくれたりしたんですよね。それまでは、事務所の方針で、あまりライブを乱発しないように言われてたんですよ。経費とイメージの問題ですね。もともと、そのマネージャーは、ジャズの山下洋輔さんのマネジメントをやってた人で、地方のライヴスポットにもコネクションを持ってたんで、辞める前にツアーをする流れを作ろうとしてくれていたんです。それで事務所を離れた'98年から、ソロとヘルツと両方で、年中ツアーを回るというような活動を始めたんです。
 T:そこからの活動の流れは?
T:そこからの活動の流れは?
リクオ:そこから今に至までは基本的な活動スタンスは変わってないですね。
ツアー回ってると、いろんな出会いがあって、どんどんネットワークが広がっていきましたね。それまでは、レコード会社とか、事務所を介していたので、ダイレクトに人と出会ってコミュニケーションする機会はそんなに多くなかったんです。事務所の人間もいない、マネージャーもいない、レコード会社の人間もいない、という状態になった時に、始めていろんな人と正面向いてつきあわなくちゃいけなくなって、それがすごく財産になってますね。いろんな人との出会いが、今の活動を支えてくれていて、人つきあいも楽しくなってきたんですよね。最初ツアーを回り出した頃は、初めて会う人が多いし、もともとそんなにしゃべる方でもなかったんで、毎日の打ち上げが辛いなとか(笑)、面倒な気持ちもあったりしたんですけどね。でも、だんだん相手の話を聞いたりするのが、嫌でななくなってきたんですよ。人それぞれの物語に触れるのも面白いし、いろんな土地、いろんな人に、その土地ならでは、その人ならではの時間の流れとか価値感があるのがわかってきたんですよ。東京にずっといると、ひとつの価値感とか流れにしばられてしまって、苦しいような感じがあったんですけど、いろんな街をツアーして、いろんな人と会うことによって、そうじゃなくていろんな生き方、価値感、時間の流れがあって、幅広く選択できるんだっていうことが肌で実感できたんですよ。それがすごくよかったですね。
T:2000年に入ったころ、変わったことは?
リクオ:自分自身の音楽の幅、興味も広がって、ミュージシャン同士のつきあいも増えて、世代とかジャンルの幅がすごく広くなったんですよね。で、そういうミュージシャン同士の縦横のつながりもできて、次第に、「自分の役割というのは、その世代とかジャンルに橋をかけるようなことではないか」と思うようになってきたんですよ。だから自分で率先してライヴ・イベントを企画するようになってきましたね。そういうさまざまな「つながり」を、音楽活動の中で意識するようになってきましたね。年齢的な部分もあったと思うんですね。30半ばで。人から求められるもの、期待されるものも次第に変わってきて。
T:「ピアノマン・ナイト」というイベント、クレイジー・フィンガーズ結成への流れというのも。
リクオ:そうやね、元々ピアノ弾き同士のつながりってあんまりなかったし、オレ自身も知り合いがそんなにいなかったんですよ。それで、たとえば鍵盤奏者ばっかり集めるイベントていうのをやれば、自分にとっても刺激になるし、いいんじゃないかなと思いまして、企画してみたらすごく面白くて。で、イベントの最後に生ピアノとデジタル・ピアノをステージに並べて、みんなで合奏するということをやってたんですよね。出演者同士のデュオのセッションもやったりしていて。それでピアノの合奏の面白さっていうのに気づいて、クレイジー・フィンガーズにつながっていったんです。
 T:クレイジー・フィンガーズの始めはどんな感じだったんですか?
T:クレイジー・フィンガーズの始めはどんな感じだったんですか?
リクオ:以前からKyonさんとふたりで、ピアノ.アンサンブルという形での活動ができたら面白いなという話をしてたんですよね。それで、まずKyonさんに「ピアニストがピアノを弾いて歌う、ピアノマンが集まったアルバムを作ってみないか」という話をもちかけたら、「ぜひやろう」ということで。それでメンバー選びをして、Kyonさんとオレ以外に、YANCY、斎藤有太、伊東ミキオというメンバーが集まって、それぞれのソロもあり、デュオもあり、全員の合奏もありというアルバムを作って、『CRAZY
FINGERS』というチーム名をつけて、レコ発のツアーに出たんですよ。でも当時は企画もののアルバムという意識があったんで、ツアーに出て赤字になったり、あんまり評判がよろしくなければ、一発ものの企画で終わるかなという感じやったんですけど、そのツアーに予想外にたくさんのお客さんが集まってくれて、非常にライヴが弾けたんですよね。
ライブをやってみて、ピアノの合奏というのがこんなに面白くて可能性があるっていうことに、メンバーもお客さんもスタッフも気付いたんですね。それで調子づいて、これはこの形を続けていこうという流れになって、今に至ってますね。
元々オレが好きだったピアノ・スタイルっていうのは、バレル.ハウスとかジューク・ジョイントて呼ばれるような黒人の居住区にある寄り合い酒場で、旅回りの黒人ミュージシャンが週末にやって来ては弾いていたピアノ。それらはダンス・ミュージックだったんですよね。それがブギと呼ばれる音楽になったり、ブルースになったりロックンロールになったりしていって。
そういうピアノ.スタイルに影響を受けながら、ピアノ.アンサンブルでやんちゃなダンス.ミュージックをやるというのが、クレイジー.フィンガーズの基本的な方向性ですね。
T:で、新しいアルバムの話なんですけど、「セツナウタ」、これを作る経緯は?
リクオ:この2年間、鍵盤を思い切り叩いて、ライブ.パフォーマンスを楽しんでっていう部分は、クレフィンの活動の中でかなり発散できたというか、出せていたので、ソロでは自分のシンガー・ソングライターとして資質が、しっかり伝わるアルバムを作ろうと考えたんですね。歌心の伝わる、弾き語りの延長線上のアルバムを作るという方向が定まると、レコーディングの過程で次第に、足していくんじゃなくて、省いてゆく、そいでゆくと作業を意識するようになりましたね。で、その結果自分の表現のコアな部分というか、一番ベースになってる部分が表に出た作品が作れたような気がします。思い入れのある作品になりましたね。
 T:この間のライヴでファースト・アルバムの楽曲をやったのは何か意味が?
T:この間のライヴでファースト・アルバムの楽曲をやったのは何か意味が?
リクオ:そうですね、自分の音楽がいろんな変遷をたどっていて、ある時期から少しこう、切れているというか。自分が変わろうという気持ちが強かったので、どこかで一回区切りをつけてしまっていたところがあったんです。
それが、今回のアルバムを作ってるうちに、自分のいろんな時代の音楽性が、無理なくスムーズにつながっていくような作品にまとまっていった気がしたんですよね。それで、今回、置き去りにしていた過去の楽曲を取り上げてみようという気になったのかもしれないですね。
T:タイトルの「セツナウタ」。これはどういう意味が?
リクオ:これは切ない気持ちの「切な」と瞬間の「刹那」のふたつの言葉をかけてるんです。この二つの言葉は、自分が表現するときの、ベースになってるキーワードかなっていう、気がするんですよね。「切ない」っていう気持ちの中には、いろんな感情が含まれているんですよね。自分は表現する時に、ただ嬉しいとか、悲しいとか、楽しいとか辛いとか、そういうシンプルな感情を伝えたいんじゃなくて、人の感情ていうのは常にいろんなものがないまぜになってると思うんですよね。「切ない」ていう言葉には、微妙なニュアンスがあって、悲しみとか喜びとか、そういう言葉では割り切れない、なんかはみ出している感情が含まれている気がするんです。自分の表現したいのはそういう部分なんですよね。
T:「刹那」っていうのは今のリクオさんの中で自然と出て来たものなんですか。
リクオ:その瞬間、瞬間が大事やっていうのは、音楽活動の中で身をもって体験してるので。ライブしていて、明日のことばっかり考えてたらステージに集中できないですからね。まず今、その場にいる皆と共鳴して共有して、化学反応を起こす。この瞬間を最高にする。そこからしか、次に進めない。今の瞬間がなければ明日がないという実感は、ますます強くなってるかもしれないですね。そういう思いが、音楽にも反映されてると思いますね。
T:最後に。これからも、旅の続きみたいな感じにはなっていくと思うんですけど、どういう感じで続いていくのかなと。
 リクオ:そうですね、とにかくずっと旅の続きみたいな感じが、いいなと思ってます。キープ・オン・グルーヴィンという感じですね。自分一人でできることが、たくさんあるんだっていうこともわかったし、人とのつながり中でしか成り立たない、自分ひとりでできないことも、たくさんあるってこともわかってきたし。今は、いろんなものとのつながりを感じながら、活動していきたですね。さっきも言ってたように、自分が橋渡しというか、ブリッジのような役割になれたらいいなと思いますね。世代とかジャンルとか、関係なくつながっていけるような、そういう活動ができたらいいですね。あとはもう、日々を楽しむことですね。楽しんだもん勝ちというか。どうせ色んなことがあるんやから。楽しんで味わって、その先に未来があると思っているので、そういう日々を積み重ねていきたいな、その中での出会いを大事にしたいし、別れもかみしめながら、続けていけたらなと思ってます。
リクオ:そうですね、とにかくずっと旅の続きみたいな感じが、いいなと思ってます。キープ・オン・グルーヴィンという感じですね。自分一人でできることが、たくさんあるんだっていうこともわかったし、人とのつながり中でしか成り立たない、自分ひとりでできないことも、たくさんあるってこともわかってきたし。今は、いろんなものとのつながりを感じながら、活動していきたですね。さっきも言ってたように、自分が橋渡しというか、ブリッジのような役割になれたらいいなと思いますね。世代とかジャンルとか、関係なくつながっていけるような、そういう活動ができたらいいですね。あとはもう、日々を楽しむことですね。楽しんだもん勝ちというか。どうせ色んなことがあるんやから。楽しんで味わって、その先に未来があると思っているので、そういう日々を積み重ねていきたいな、その中での出会いを大事にしたいし、別れもかみしめながら、続けていけたらなと思ってます。
T:今回は長い時間、ありがとうございました。
リクオ:ありがとうございました。
前回 PART1へ>>>>>>>>>>
リクオさんについて詳しいインフォメーションは、オフィシャルHP(http://www.rikuo.net/)まで。